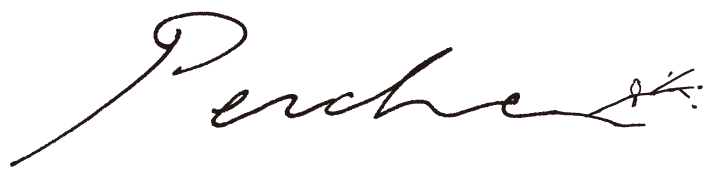2023/10/12 19:42
京都の美大で陶芸を学び、唐津で3年の弟子入り修行を経て独立。
滋賀県に工房を構え、磁器のうつわを制作されている鈴木まどかさん。
やわらかで、それでいて凛としていて、優しさと凛々しさのバランスが絶妙なうつわ。
まどかさんの作品をはじめて拝見したときの印象です。
まどかさんとの出会いは運命的で、ペルシュ店主が京都をぶらついていた時に、偶然立ち寄ったギャラリーで展示会をされていたのがはじまり。滋賀で作陶されている作家さんが京都で展示会をされていたというシチュエーションで、まさか共通項があるとは思いもしませんでしたが、なんとなんと東三河のご出身でペルシュ店主と同じ高校の後輩でした!!
その衝撃の出会いから月日は流れ、今や数多のギャラリーからお声のかかる人気ぶり。
お忙しい合間を縫って、工房訪問のお時間をいただきました。
取材(文、写真)うつわペルシュ
磁器の面取りからはじまった器づくり

ペルシュ:
陶芸家への志しは、高校生のときから芽生えていたのですか?
まどかさん:
「ものづくりがしたい」という漠然とした気持ちはありました。
あと京都という土地に憧れもあったので、京都の美術系の大学に進路を決めました。
ペルシュ:
「陶芸家になる!」というより、「まずはそっちに振ってみよう」というスタートだったんですね。
まどかさん:
あんまり深く考えてなかったですね(笑)
でも、いざ大学に入ってみると、自分の中で想像していた「陶芸コース」と美大のそれはイメージが違っていて、オブジェだったりコンセプトがどうのとか、そういうのがすごく強くて、けっこうギャップに感じていた時もありました。
ペルシュ:
陶芸家になろうと決めたのは、なにかきっかけがあったのですか?
まどかさん:
陶芸作家を意識しだしたのは大学3年生の時。学校の授業で伝統工芸の作家さんのところに行って勉強する機会があって、そば猪口を作る授業だったんですけど、その作家さんが青白磁で面取りをされている方で。その時の、作品を作られている風景や後ろ姿を見たときに胸にぐっと来るものがありました。それまでは「陶芸で食べていくぞ!」という覚悟はそんなになくて、なんとなく続けていければいいなというかんじだったのが、本気になったのはその時でしたね。
ペルシュ:
最初のころはどんな作品を作っていたんですか?
まどかさん:
学生時代を含めて8年間京都に住んでいたんですけど、その8年間は磁器の面取りしかできなかったんですよ。
大学を卒業してから釉薬の勉強をするところに行って、そこでもずっと面取りしていましたね。そのあと2年間、共同工房を借りてアルバイトしながら制作していた時も、いろんなものを作ってみたりするんですけど、どうしてもこういう作風から抜けられなかったし、京都にいると鉄粉や歪みが気になるという評価で、磁器とはそういうものなんだと思い込んでいました。
あと、手に取ってもらいやすい値段のうつわを作りたくても、自分のやっている磁器の面取りはすごく時間も手間もかかる伝統工芸寄りなうつわで、値段が高くなってしまう。
そういったことで、けっこう悩んでたりもしていたんです。
そんなときに知人から弟子入りの話をいただきました。

初期のころに作っていた作品。一番右は大学の卒業制作で作ったもの。
混じりけのない磁器土を使い、総削りの面取りで仕上げられたシャープな作品。
弟子入り修行で見えた景色
佐賀県唐津市の天平窯 岡晋吾氏のもとで学ぶことになったまどかさん。大きく作風が変わるきっかけとなった弟子入り修行時代に見えたものは・・・
ペルシュ:
それで唐津での修業が始まったんですね。
修業時代は振り返ってみてどうでしたか?
やはり大変?
まどかさん:
大変は大変でしたね。
でも、その修業時代に作陶はもちろん窯のスケジュールを考える、作品リストを作る、梱包から発送とすべてやってきたおかげで、独立してすぐ修業時代の動きのままやれていますから、身には付きましたね。

奥:初期のころに使っていた窯
手前:工房移転時に譲り受けた大きな窯。年代不明という年季の入ったもの。

窯から出てきばかりのたうつわたち。
うまく焼けなかったものは瞬時に判断して逆さにしてある。
ペルシュ:
唐津での修行で一番の学びだったという収穫は一言で言うと何ですか?
まどかさん:
「自由に作っていいんだ!」という気づきが一番ですね。
「磁器はこうでなければいけない」みたいな固定概念が京都のなかではあったので。
磁器でこれだけ自由に動かしていいんだとか、こんなにゆるくしていいんだとか。

磁器は本来「総削り」で全部削ってきれいに仕上げるが、
まどかさんの作品はやわらかい動きを残している。

「動きのある削り」は土が柔らかいうちに削らないとできない。
高台に刻まれた線がきっちりと一周していないのもまどかさんの表現。
ペルシュ:
京都を出て見えたものがあったということですね。
磁器土になにかを混ぜるのもそのころから?
まどかさん:
今ではむしろ買ってきた磁器土そのままではすごく味気なく感じてしまって。

工房で見せていただいた土

左手は初期のころの総削りでシャープな作品。
右手は土の柔らかさを残したあたたかみのある作品。

土をブレンドしたり、絵を彫ったり、やわらかい印象に変化しているのがわかる。
苦手意識から生まれた作風
以前と比べると、満足のいく表現ができるようになったという実感が得られつつあると語るまどかさんの作品は、やわらかで温かみのある独特な絵付けが今や代名詞のようになっていますが、意外な言葉が!
まどかさん:
デッサンをならっていたわけでもないし、弟子入り先でも絵付けはノータッチだったので、絵付けに対するコンプレックスが実はあるんです。
ペルシュ:
驚きです。この作品たちの絵付けは独学で?
まどかさん:
うつわのなかに色は欲しかったので。
でも絵が苦手だから、呉須*で描いて流してみようと(笑)
あと絵を描くのではなく、彫る。彫って色を入れればちょっと自分の苦手意識が
薄らぎます。彫ったところに釉薬が溜まるのもいいかんじで。
*呉須・・古くから染付などの磁器に使われている青色の顔料。

絵付けをする前に彫って絵を刻む。

「これが最近のブーム!」と見せてくれた作品。
全体に鎬(しのぎ)を施し、彫った絵に呉須で色を入れたもの。
ペルシュ:
釉薬が溜まって緑色のガラス質になったところもたまらなく良いですね!
まどかさん:
削るのはやっぱり好きなので鎬(しのぎ)*も好きです。
*鎬(しのぎ)・・表面を削って作る稜線文様の装飾。
ペルシュ:
型の作品も素敵ですよね。
まどかさん:
型も削って作るものなので、型作りは好きな作業です。
ペルシュ:
結論!削るのが好き!(笑)

自ら制作している型もバラエティ豊か。

型を使って「型打ち」をするまどかさん。


一枚のうつわが完成するまでに、想像を超える手間がかかる。
陶芸家 鈴木まどかさんの世界に触れて

土間に置かれた地下足袋が可愛らしくてつい撮影。
「作品の雰囲気と本人のイメージにギャップがあるとよく言われるんです。」
とおっしゃるまどかさん。
確かに、ショートヘアのきりりとした第一印象と、作風の一部であるやわらかな雰囲気は、一見対局なイメージかもしれません。
しかし、今回の取材を通して、鈴木まどかという作家は、表現の空をどこまでも自由に軽やかに飛んでいきたいと望み、型に縛られないという翼を手に入れた今、「つくりたいものがワーッと出てくる!」とおっしゃるように、湧き出す創作意欲のままに作品を生み出しており、一つのイメージでは語れないと感じました。
カッコいい作品も、可憐でかわいらしい作品もあれば、シンプルなものも装飾的なものも混在します。一人の作家から生まれたと思えないほど多様な作風の引き出しを持ち、「縛られない」という自由が貫かれた多様な表現こそが鈴木まどかの世界観なのでしょう。

工房は落ち着く古民家
そして、どのうつわも「料理が映えるだろうな」と感じさせることから、使うときの目線をお持ちの作家さんだろうと想像していました。
お茶を出してくれた時に「やっぱり!」と確信に。

まどかさんのうつわで、うれしいおもてなし ^^
2023年11月にはペルシュで鈴木まどかさんの個展を開催いたします。
全国各地で作品が見られるようになって、実は初の地元での個展です!
鈴木まどかさんの世界をたくさんの方に感じていただけるとうれしいです。

【つくり手Profile】
鈴木まどか(すずき まどか)
愛知県豊川市出身
愛知県立国府高校卒業
京都精華大学 芸術学部 陶芸コース卒業
京都市産業技術研究所 陶磁器応用コース修了
京都の共同工房にて制作
佐賀県唐津市 天平窯 岡晋吾氏に学ぶ
滋賀県に工房を構え独立